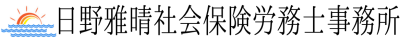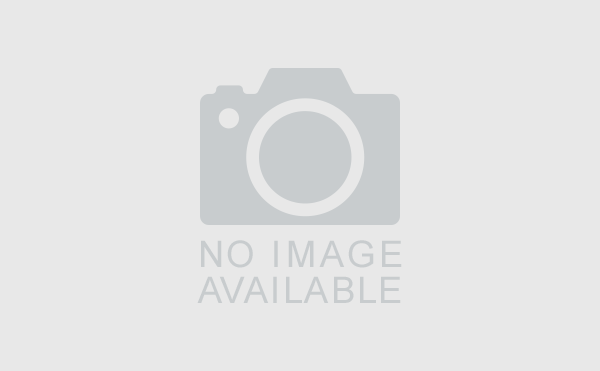所長からの今月のひとこと【㉗】~実際にあった労働相談より~
第27回は、「副業兼業」についてです。
「働き方の多様化」「物価高騰による実質収入減」等々の社会情勢から、又、「終身雇用の終焉によるキャリア形成の必要性が増している」労働環境から、「副業兼業」の必要性が日々高まっています。
企業側も「人件費の高騰」等の事情から、「副業兼業」を認める方向にあります。
厚生労働省も現在、「労働時間の通算の見直し」等、複雑な労務管理を避け現在の働き方に合わせるために、法改正に向けて検討に入っています。
「情報の漏洩」等の問題を抱えていますが、今後「副業兼業」に関して大きく変わると思われますので、現在の基本的ルールをおさらいしておきましょう!
副業・兼業とは?
〇 副業・兼業を行うということは、二つ以上の仕事を掛け持つことをここでは想定しています。 副業・兼業は、企業に雇用される形で行うもの(正社員、パート・アルバイトなど)、自ら起業して事業主として行うもの、コンサルタントとして請負や委任といった形で行うものなど、さまざまな形態があります。
但し、後述の「労働時間の通算」に関しては、労働者+個人事業主のようなケースは該当しません。
副業・兼業にはどんなメリットと留意点
〇 副業・兼業を行うことのメリットは、働く方の状況によってさまざまありますが、たとえば、以下 のようなものが考えられます。
・ 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、主体的にキャリア 形成ができる。
・ 既に行っている仕事の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求できる。
・ 所得が増加する。
メリットの一方で、注意をしなければいけない点もあり、たとえば、以下のようなものが考えられます。
・ 就業時間が長くなる可能性があるため、自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である。
・ 副業・兼業によって既に行っている仕事に支障が生じないようにすること、既に行っている仕事と副業・兼業それぞれで知り得た業務上の秘密情報を漏らさないことなどに留意する必要がある。
1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合に、雇用保険等の適用がない場合があることにも留意が必要です。
労働時間通算の原則的な手順
ステップ①:所定労働時間の通算
所定労働時間は、契約の先後の順に通算します。
所定労働時間を通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、時間的に後から労働契約を締結した企業が自社の36協定で定めるところによってその時間外労働を行わせることになります。
ステップ②:所定外労働時間の通算
所定外労働時間は、実際に所定外労働が行われた順に通算します。
自社の所定外労働時間と副業・兼業先における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算します。
所定労働時間の通算は、労働契約締結の先後の順となっており、所定労働時間と所定外労働時間で通算の順序に関する考え方が異なる点に注意してください。
自社と副業・兼業先のいずれかで所定外労働が発生しない場合の取扱いは、以下のとおりです。
・ 自社で所定外労働がない場合は、所定外労働時間の通算は不要
- 自社で所定外労働があるが、副業・兼業先で所定外労働がない場合は、自社の所定外労働時間のみ通算する
通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、そのうち自ら労働させた時間について、自社の36協定の延長時間の範囲内とする必要があるとともに、割増賃金を支払う必要があります。
その他のポイント
・就業規則を整備する必要がある
・「管理モデル」の活用
管理モデルとは? 副業・兼業の日数が多い場合や、自社と副業・兼業先の双方で所定外労働がある場合などにおいては、 労働時間の申告等や労働時間の通算管理において、労使双方の手続上の負荷が高くなることが考えられ ます。管理モデルは、そのような場合において、労使双方の手続上の負荷を軽くしながら、労働基準法 に定める最低労働条件が遵守されやすくなる方法です。但し採用する際は、事業場間の協力が必要になります。
・健康管理の実施
〇 企業と労働者がコミュニケーションをとり、労働者が副業・兼業による過労によって健康を害したり、現在の業務に支障を来したりしていないか、確認することが望ましいです。
〇 使用者は、労使の話し合いなどを通じて、以下のような健康確保措置を実施することが重要です。
・ 労働者に対して、健康保持のため自己管理を行うよう指示する ・ 労働者に対して、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝える ・ 副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置を実施する ・ 自社での労務と副業・兼業先での労務との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や抑制を行う
今後、「労務管理」「情報管理」がより高度なものを求められていく可能性が高いので、是非ご一読いただくとともにお気軽にご相談ください!